こんにちは、田中です。
固定資産税は、1月1日時点、不動産を所有している人に課税される税金です。もし1月2日に不動産購入した人には税金がかからないのですが、さすがに不公平なので不動産産売買契約上は固定資産税清算金として、1年分の固定資産税を日割り計算して、買主から売主へ支払います。

そのため、もしも1月1日に不動産を持っていて、1月2日に火事で家燃えてしまった場合も固定資産税ははかかってしまうのです。
固定資産税をかけるもととなる評価額は3年に1度見直しされます。家屋の評価額は、時の経過とともに価値が減ってくると思われる方が非常に多いですが、実は上がるケースもあるってご存じでしょうか。、固定資産税評価の付け方に秘密が隠れており、もし新しく建物を建てるとしたらどのくらいコストがかかるか、という考え方をとっていますので、その時点での原材料費が加味されます。
最近は、原材料費が高騰していますので、時の経過で建物の価値は下がる一方、もう一回その材料費を揃えようとしたらコストが高くなるという関係で、固定資産税評価額が高くなるという現象が起こり得ます。ですので、固定資産税評価額が上がったからとって、自治体が間違えてるんじゃないか、と思われがちですが、ここは注意が必要です。
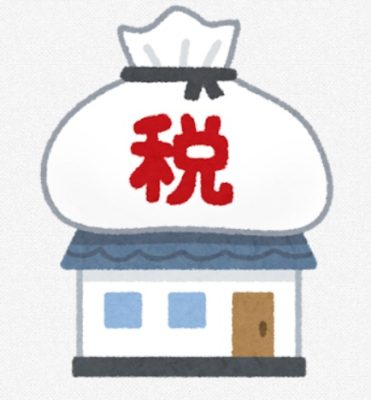
共有所有不動産の場合には、連帯納税義務になります。共有で不動産持っている場合、持ち分に応じて納税額が決まるというわけではなく、共有者のうち誰が納税しても構わないとされています。
新築家屋は、3年分固定資産税が1/2に減額されます。4年目から減額が無くなり固定資産税が高くなりますので、注意が必要です。ちなみに、3階建以上の耐火・準耐火建築物は5年分が1/2に減額されます。
評価が非常に低くつけられてる不動産について、1つの自治体の合計額が土地30万円・家屋20万円以下になると、固定資産税がかかりません。昔、バブルのとき、原野商法というものが流行りました。ここは将来リゾート開発で値上がりするから、今のうち買っておいたお得ですよ、といったことで、地方の土地を投資目的で買った人がたくさんいらっしゃいます。しかし、結局開発されずにただの山とか原野になってしまっている不動産がたくさんあり、そういった土地は免税点以下なので固定資産税がかかっていないケースが非常に多くあります。固定資産税がかからないと、毎年固定資産税の通知が来ないので、そのような土地の存在を忘れてしまうことも。家族もそのような土地を所有していることすら知らないので相続税申告をするときに不動産が申告漏れになるケースがあるそうです。相続税申告をするときには、免税点以下の不動産にも相続税がしっかりかかってきますので、注意が必要です。
税率は 1.4% (都市計画税 0.3%)が固定資産税評価額に加算されます。ただし、市町村ごとに条例で変更できるというルールになってます。以前は上限税率(2.1%)がしたが、2004年の税制改革で廃止されました。ですが、無限に上限適用されているかといえば、現在は全国のほとんど9割以上の市町村で1.4%の税率を採用しています。東京都23区も1.4% (都市計画税 0.3%)になっています。
固定資産税評価額とは、固定資産税の金額を決めるために、市町村が独自に決定しているものです。実際に市町村が土地を見に行って現地調査をして計算をしていますが、概ね公示価格の70%くらいが目安になっています。ただし、実際は土地の形状や建物の面積で決まりますし、あとは新築住宅の建物の場合は、工事にかかった金額のだいたい50~60%くらいが目安になっていると言われています。基本的には公示価格の70%くらいが目安なんだな、というイメージをもっていただければ問題ないと思います。
固定資産税には、皆さんにはうれしい評価減の特例があります。これは皆さんが申請しなくても、市町村が調べて適用してくれます。土地のパートと建物のパートに分かれています。
小規模住宅用地(200㎡以下の部分) : 固定資産税評価額(標準課税) X 1/6
一般住宅用地(200㎡を超える部分) : 固定資産税評価額(標準課税) X 1/3
たとえば、 300㎡ → 200㎡ = 1/6、100㎡ = 1/3 となります。
マンションのような集合住宅は、敷地全体の面積を戸数(部屋の数)で割り算して計算します。
1Rのような区分マンションを購入する場合は、一戸200㎡以下なので、1/6が適用される場合がほとんどになります。
たとえば、固定資産税評価額が1200万円だった場合は、固定資産税は以下の計算になります。
1,200万円 X 1/6 X 1.4% = 28,000円
3階建以上の耐火、準耐火構造住宅 : 新築後5年間
上記以外の一般住宅 : 新築後3年間
該当の建物は何れも評価が 1/2 になります。最近の1R新築区分マンションであれば、基本3階以上の耐火構造なので、5年間は建物の評価が 1/2 になると思っていただいて差し支えないかと思います。
固定資産税と一緒に、都市計画税が課税されます。都市計画税は、都市計画区域内の土地・建物が対象になります。都市計画区域とは、より住みやすい街つくりのために都市計画が実施される区域のことで、日本国土のうち、だいたい25%が該当し、日本人口のおよそ90%以上が住んでいるとされています。固定資産税と同様に、毎年1月1日時点の所有者に課税され、税率は0.3%ですが、市町村ごとに条例で変更できるとされています。
小規模住宅用地(200㎡以下の部分) : 固定資産税評価額(標準課税) X 1/3
一般住宅用地(200㎡を超える部分) : 固定資産税評価額(標準課税) X 2/3
相続税の不動産(土地・家屋)の評価に必要な固定資産税については以下の通りです。
まず、相続税の計算で土地や建物を評価するときに、固定資産税課税明細書をお手元に準備ください。
固定資産税の課税明細書に明記されているのは、大きく分けて以下の2点です。
①固定資産税の納付税額
②固定資産税の計算根拠になる土地と建物の詳細情報
(所在・面積・評価額等)
つまり、固定資産税を払うための情報しかありませんが、相続税の土地・建物を把握するのに重要な情報も詰まっています。
次に市町村ごとの「固定資産税の路線価」を調べます。路線価とは、道路に面している宅地の1㎡あたりの評価額のことです。路線価と言っても、固定資産税の路線価と相続税の路線価と2つあります。全くの別物ですので、確認するときは注意してください。ちなみに、相続税の路線価は国税庁が発表するもので金額も異なります。
土地について、面積を確認します。気を付ける点は、、『登記地積』と『現況地積』と面積が2つあります。
どちらを使用するかという点です。違いがなければ問題ありませんが、異なるケースも稀にあります。登記地積とは、法務局で最初に土地の登録をされた当時の情報です。
これに対して、現況地積は、現在の土地の地積となります。そのため、現状の土地の情報が実態を反映しますので、『現況地積』を使って土地評価額を算出しましょう。
相続税で使用する面積(地積)を把握しましたら、路線価を調べます。
路線価については、下記のページから面積×路線価で土地の評価額を算出していきます。
家屋の評価額について、相続税の家屋の評価額は非常に簡単です。
固定資産税上の家屋の評価額=相続税の家屋の評価額となります。
(ただし、賃貸している家屋を除きます。)
なお、1点注意していただききたいのが、区分所有マンションを所有している方です。
区分所有マンションは、1棟のマンションの1室を所有していることになりますので、先ほどの課税明細とは確認すべき点が異なります。
課税明細書のうち、『評価額』と『課税標準額』は同額ではありません。
こちらの評価額部分は、マンション1棟全体の評価額を明記しています。一方、課税標準額が、所有している1室部分の評価額となります。相続財産の対象は、1室部分だけなので、『課税標準額』が評価額となります。金額を間違えないようにしましょう。
ご自身で申告を検討している方は、ぜひ参考にして見て下さい。
ご来店予約と、メールでのご質問もこちらから
不動産査定AIが即査定額をお答えします無料
※かんたんAI査定は物件データベースを元に自動で価格を計算し、ネットで瞬時に査定結果を表示させるシステムです。